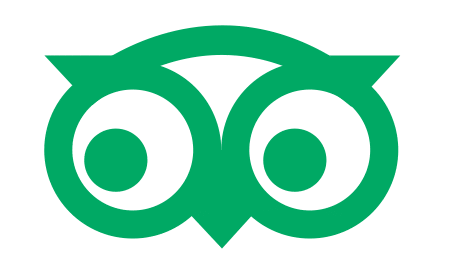的点评
18分ほどの上田城と真田家の歴史ビデオが観られます。
Uedajo Minamiyagura Kitayagura Yaguramon的点评
点评:1994年、110年ぶりに復元されました。
門の右側には、高さ2.5 × 幅3 mほどの巨大な石があります。これは「真田石」と呼ばれるものです。城の入り口には、よくこのように城主の武力や財力を誇示するために大きな石が置かれます。城を訪れる大名がその石の大きさを褒めることが、礼儀の一つだったと言われています。
関ヶ原の合戦後破却された上田城は仙石氏が城主の時代に再建され、7基の櫓(やぐら)と2基の櫓門が建てられました。
明治維新後、西櫓1基を残しそのほかの櫓・櫓門は取り払われました。城外に移築されていた2基の櫓は後に買い戻され、昭和18年(1943)から24年にかけて現在の南櫓・北櫓として再移築されました。平成6年(1994)には東虎口櫓門が復元されました。
3棟ともに規模は全く同じで、一階は桁行9.85m、梁間7.88m、二階は桁行8.64m、梁間6.67mです。二階は一階より二尺(60.6cm)ずつ内側に入れた梁の上の土台に柱を立てています。つまり、一・二階を通している柱はなく、一階の上に縦横とも四尺ずつ縮小した二階を、そっくり乗せた形となっています。屋根は入母屋造りで本瓦葺です。
外の壁は一・二階ともに下の3分の2ほどを横板張りとし、その上から軒下の部分は、そっくり土壁でおおう「塗籠」としています。この形は寒冷地に多く、また初期城郭建築の様式でもあります。上田城の櫓は初期の建物ではありませんが、真田氏創建当時の古い形式にならっているのかもしれません。城の修築は元通りに直すことが原則であったことからみても、真田昌幸の建てた櫓も同様のものだった可能性は高いと言えましょう。
門の右側には、高さ2.5 × 幅3 mほどの巨大な石があります。これは「真田石」と呼ばれるものです。城の入り口には、よくこのように城主の武力や財力を誇示するために大きな石が置かれます。城を訪れる大名がその石の大きさを褒めることが、礼儀の一つだったと言われています。
関ヶ原の合戦後破却された上田城は仙石氏が城主の時代に再建され、7基の櫓(やぐら)と2基の櫓門が建てられました。
明治維新後、西櫓1基を残しそのほかの櫓・櫓門は取り払われました。城外に移築されていた2基の櫓は後に買い戻され、昭和18年(1943)から24年にかけて現在の南櫓・北櫓として再移築されました。平成6年(1994)には東虎口櫓門が復元されました。
3棟ともに規模は全く同じで、一階は桁行9.85m、梁間7.88m、二階は桁行8.64m、梁間6.67mです。二階は一階より二尺(60.6cm)ずつ内側に入れた梁の上の土台に柱を立てています。つまり、一・二階を通している柱はなく、一階の上に縦横とも四尺ずつ縮小した二階を、そっくり乗せた形となっています。屋根は入母屋造りで本瓦葺です。
外の壁は一・二階ともに下の3分の2ほどを横板張りとし、その上から軒下の部分は、そっくり土壁でおおう「塗籠」としています。この形は寒冷地に多く、また初期城郭建築の様式でもあります。上田城の櫓は初期の建物ではありませんが、真田氏創建当時の古い形式にならっているのかもしれません。城の修築は元通りに直すことが原則であったことからみても、真田昌幸の建てた櫓も同様のものだった可能性は高いと言えましょう。
翻译:1994年时隔110年修复。
大门右侧有一巨石,高约2.5米,宽约3米。这就是所谓的“真田石”。城堡入口处常放置一块大石头,以彰显城堡领主的军事实力和财力。据说,参观城堡的封建领主称赞石头的大小是出于礼貌。
上田城在关原之战后被毁,在战国先生任城主期间重建,建造了七座角楼和两座角楼门。
明治维新后,除西塔楼一座外,塔楼和矢车门都被拆除。搬迁到城堡外的两座炮塔后来被买回,并于1943年至1949年间搬迁为现在的南炮塔和北炮塔。 1994年修复东虎口八仓门。
三栋建筑的规模完全相同:一层梁排9.85m,梁距7.88m,二层梁排8.64m,梁距6.67m。在二楼,柱子竖立在从一楼向内设置二尺(60.6厘米)的梁的基础上。也就是说,第一层和第二层没有柱子穿过,将纵横都减少了四尺的第二层放在了第一层之上。屋顶是人字形和瓦片。
一、二层外墙下三分之二为横板,从檐上至檐下全为漆筐泥墙。这种形式多见于寒冷地区,也是早期城堡建筑的一种风格。上田城的炮塔并非早期建筑,但可能是仿照真田城建城时的旧式建筑。从城堡恢复原状的原则来看,真田正之所建的炮塔极有可能是相似的。
大门右侧有一巨石,高约2.5米,宽约3米。这就是所谓的“真田石”。城堡入口处常放置一块大石头,以彰显城堡领主的军事实力和财力。据说,参观城堡的封建领主称赞石头的大小是出于礼貌。
上田城在关原之战后被毁,在战国先生任城主期间重建,建造了七座角楼和两座角楼门。
明治维新后,除西塔楼一座外,塔楼和矢车门都被拆除。搬迁到城堡外的两座炮塔后来被买回,并于1943年至1949年间搬迁为现在的南炮塔和北炮塔。 1994年修复东虎口八仓门。
三栋建筑的规模完全相同:一层梁排9.85m,梁距7.88m,二层梁排8.64m,梁距6.67m。在二楼,柱子竖立在从一楼向内设置二尺(60.6厘米)的梁的基础上。也就是说,第一层和第二层没有柱子穿过,将纵横都减少了四尺的第二层放在了第一层之上。屋顶是人字形和瓦片。
一、二层外墙下三分之二为横板,从檐上至檐下全为漆筐泥墙。这种形式多见于寒冷地区,也是早期城堡建筑的一种风格。上田城的炮塔并非早期建筑,但可能是仿照真田城建城时的旧式建筑。从城堡恢复原状的原则来看,真田正之所建的炮塔极有可能是相似的。
此点评仅代表旅行者个人的主观意见,并不代表TripAdvisor以及其合作方的意见。
关于我们
|
新闻动态
|
商务合作
|
会员中心
|
业主中心
|
业主通
|
常见问题
|
意见反馈
|
联系我们
|
营业执照
© 2026 Tripadvisor 版权所有。
使用条款 |隐私政策 |网站工作原理
部分照片由 VFM Leonardo 提供。
* Tripadvisor不是旅行社,也不是旅游预订服务代理商。我们提供免费、客观、公正的旅游资讯服务。 (显示更多)
TripAdvisor LLC 既不是预订代理商,也不是旅游运营商,不会向网站用户收取任何服务费。 按照规定,在 Tripadvisor 发布机票价格、游览和旅行套餐的合作伙伴(航空公司、旅行提供商及预订代理商),其标价须包含所有费用和附加费用。 例如, 机场出入境税费、消费税与其他服务费、手续费、杂费及附加费用。 当您向我们的某个合作伙伴进行预订时,请务必查阅他们的网站以了解当地行政部门要求的所有适用费用的具体情况。 除非另有说明,机票价格通常指的是一个人的价格(以人民币计)。
为方便起见,TripAdvisor LLC 根据从我们的预订合作伙伴获取的空房率计算每个酒店的均价。 对于游览和景点来说,所显示价格通常是每位成人的最低可用价格。 对于列出的任何旅行套餐或优惠,TripAdvisor LLC 无法保证任何特定的费率或价格。 此外,酒店均价每晚会更新,并以您的首选币种表示(使用现行汇率)。 由于这些已换算的价格是预估价格,因此,有关具体金额和币种请与预订网站进行核实。
此外,TripAdvisor LLC 无法保证我们网站上宣传的价格随时有效。 标价可能需要预订一定天数才能生效,或有不可用日期、使用条件或限制。
TripAdvisor公司对外部网站的内容一概不负责。优惠价格中不含税和其他费用。
ICP证:沪B2-20200433
沪ICP备20013175号
 沪公网安备31010502005427号
沪公网安备31010502005427号鹰程信息技术(上海)有限公司
货币/国家及地区
¥CNY
中国